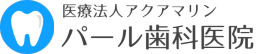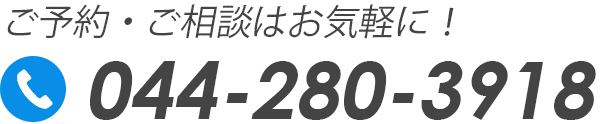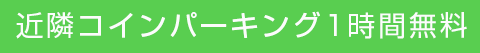咀嚼について
こんにちは。
川崎区小島新田のパール歯科医院です。
本日は咀嚼について書かせていただきます。
咀嚼(そしゃく)、
一般的にはあまり聞きなれない言葉ですが、
皆さんは何を連想されるでしょうか?
咀嚼とはお口の中に運ばれてきた食べ物を
飲み込めるように
細かく噛み砕くことを言います。
食べものを体内に取り込むための、
最初の消化活動です。
咀嚼することは食べ物の消化・吸収を
助けるだけでなく、顎の成長発育、
脳を活性化させる
重要な役割も果たしています。
人は咀嚼する事で顎が発達し、
発達した顎でさらに噛み砕くことで
食べ物を体にとりこみます。
古くから日本人は狩猟をして、
動物や魚からもタンパク質を摂っていました。
そして田畑を耕して農作物を収穫し、
大麦・あわ・はと麦などの雑穀を
主食として食べてきました。
雑穀は白米と比べて硬く、
たくさん噛む回数が必要とされます。
縄文時代では雑穀を食べており、
雑穀は口の中で唾液と混ぜて
でんぷんが麦芽糖に変化するまで
咀嚼していたと考えられています。
それに比べ現代の日本人は
咀嚼の回数が少なく、
顎が細くなり退化しています。
その理由は西洋の文化の影響から、
皆さんが大好きなパン、ハンバーグ、
スパゲティー、ラーメン、
カレーライスなどの食事が、
硬い食べ物を食べる食文化から
柔らかいものを好んで食べる習慣に
変化したために、
現代の日本人の噛む回数が
減ってしまったと思われます。
幼いうちから
軟らかいものばかり食べていると、
顎が発達しなくなってしまいます。
現代人より顎が発達していた
縄文人や弥生時代の人たちは、
1回の食事に行う咀嚼回数は
なんと4000回以上でした。
鎌倉時代では約2500回で、
江戸から戦前だと約1500回~1400回に
減少しています。
現代人はその半分以下の600回。
また、人が1回の食事に行う咀嚼回数は
約1500回以上が理想といわれています。
子どもの時から
しっかり噛む習慣をつけることで
顎の骨は発達し、消化を助けるのはもちろん、
不正咬合や顎関節症などを
未然に防ぐことができます。
さらには脳に刺激を与え、
大脳の反応を早くするといわれています。
咀嚼するということは、
人間だけではなくて地球上の動物が
生きていくために行う必然的な行動です。
咀嚼する事で
もたらされる効果をまとめると、
・顎を発達させ歯を丈夫にする
・食べ物の消化吸収を助ける
・唾液の分泌を促す
・集中力を高め、ストレスを緩和
・認知症の予防
このような事が期待されます。
このように咀嚼は
健康のために大切なことです。
健康な歯が健康な身体をつくるので、
口腔ケアをこころがけましょう。
好き嫌いなく、時間をかけよく噛んで
食べる食事こそが現代の我々にとって
必要なことではないのでしょうか?
虫歯
こんにちは。
川崎区小島新田のパール歯科医院です。
前回のブログで虫歯と食事の関係について
書かせていただきましたが、
今回は少し掘り下げて
虫歯のでき方について
詳しく書かせていただきますね。
虫歯のできかたはご存知ですか?
自然にできるようですが、
やはりそれだけではありません。
このできかたを知っていると、
誰でも十分虫歯予防ができると思います。
口の中では、まず食物のカスが
虫歯菌によって歯垢(プラーク)という
虫歯菌の巣になります。
そして巣である歯垢(プラーク)の中で、
虫歯菌はどんどん繁殖してしまうのです。
この虫歯菌は、
繁殖する際に食べ物の中の
「砂糖」や「炭水化物」などを
栄養(エサ)とします。
そして「酸」を作るのです。
この酸によって、
歯の表面(エナメル質)から
ミネラル成分が溶けだします。
これが虫歯の始まりなんです。
もう少し詳しく説明しますね。
歯の表面に住む、
ごく少数の虫歯菌(ミュータンス菌)は、
食物中の砂糖や炭水化物を分解し、
ネバネバの物質を作ります。
この物質はグルカンといい、
そのつよいネバネバが
虫歯菌が歯の表面にくっつくのを
助けてしまいます。
やがてそこには虫歯菌に限らず、
歯周病菌等の多数の細菌が
住み着くようになり、
細菌の巣(プラーク)が作られていきます。
プラーク中の虫歯菌は、
食物中の砂糖、炭水化物などを
取り込んで分解し、酸を作ります。
また虫歯菌以外にも、
同じように糖を分解して
酸を出す細菌はいます。
この酸によって歯表面のエナメル質が
溶かされて虫歯になるのです。
ところで虫歯になりやすい人、
なりにくい人がいるのをご存知でしょうか?
もともと、
歯の表面のエナメル質の密度が高い人、
低い人というのがいます。
虫歯になりやすい人は、
特にこのエナメル質の密度が低いのです。
これはもって生まれたものですが、
フッ素を上手に使えばある程度
歯を強くすることが可能です。
それと時間です。
歯の表面が汚れても、
虫歯菌の活動が活発になって
酸を産出するまでは
24時間程度かかるといわれています。
上の図を見て下さい。
虫歯になる原因は、
1、虫歯菌 2、砂糖 3、歯質 4、時間
ということになります。
この4つが重なっている部分が虫歯です。
これらのことを意識して生活すると、
虫歯は自分でも予防ができるのです。
例えば、虫歯の食料になる砂糖を控えたり、
食事をしたらすぐに歯を磨いて、
虫歯の住処になってしまう
汚れをしっかり取り除くことなど、
出来ることから
意識しておこなってみて下さいね!
虫歯になりにくい歯
こんにちは。
川崎区小島新田のパール歯科医院です。
歯磨きが虫歯予防の
基礎中の基礎であることは当然ですが、
今回は歯磨きからすこし離れて、
お話を進めていきたいと思います。
歯をしっかり磨く他にも、
虫歯になりにくい、
規則正しい食生活を送ることが大切です。
食べ物を口にして、
虫歯菌が反応して口の中の酸の濃度が
最もあがるのが、食後5分から20分です。
以前のブログで書いた通り、
その酸が歯を溶かして虫歯ができます。
これを脱灰といいます。
その後新しい唾液が出ることで
徐々に酸の濃度は下がり、
唾液によって溶けた歯は自然と元に戻ります。
これを再石灰化といいます。
ごく初期の虫歯は自然と治ってしまうのです。
これを表したのが上図の
ステファンカーブといいます。
だらだらと時間をかけて食べ続けると
常に口の中が酸性になってしまい、
虫歯になりやすくなるのです。
この図をご覧下さい。
上の赤い部分が歯が酸によって
溶けている時間です。
溶けた歯が唾液によって
戻る場合もありますが、
食事やおやつの回数が多いと
歯が酸に溶かされる時間が長くなり、
虫歯のリスクが増えてしまいます。
口に入れるものの「量」よりも
「回数」が虫歯になる原因となるのです。
規則正しい食事やおやつをとることで、
虫歯は予防できるのです。
また、一生のうち虫歯になりやすい時期
というのがあります。
永久歯の生えたての時期です。
つまりお子様の乳歯が抜けて
生え変わる頃です。
生えたての歯は、
フッ素のコーティングがないのです。
生えたての歯は質が弱いため、
時間をかけて成熟して強くなります。
年月がたつと食物(緑茶や海産物)
に含まれるフッ素が自然と歯の表面を
コーティングしてくれて歯が強くなります。
永久歯は6歳位から生え始めますので、
10代の前半を虫歯にせずに
乗り切ることができるかどうかで
歯の一生が決まってしまうんです。
矯正治療をする機会が多いこの時期に、
正しい生活で虫歯を予防していきましょう。
では虫歯予防のポイントをまとめますね。
①歯磨きで歯垢を取り除く
②食事、おやつは回数や時間を決めて食べる
③フッ素で歯を強くする
以上の3点です!
お子様が小さい頃から
歯医者に通って慣れさせてあげるのも
良いかと思います。
歯が生え始めたらフッ素を塗って予防したり、
歯並びなどをチェックしてもらいましょう。
小さいうちからしっかり予防して、
一生自分の歯で食事しましょうね。
パール歯科医院では
そのお手伝いをさせていただきます。
歯が欠けてしまった時は
こんにちは。
川崎区小島新田のパール歯科医院です。
今日は歯が折れたり、欠けたりした場合の
対処方法について書かせていただきます。
毎日の生活の中で、
思いかけず歯を何かにぶつけてしまい、
歯が欠けてしまったり、
折れてしまったりといった
経験のある方がいらっしゃるかと思います。
そんな方に対処法などを
説明させていただきますね。
歯が欠けてしまったりする要因
・転倒、スポーツ、
交通事故等のアクシデントにより、
歯が欠けたり折れたりする外傷によるもの
・虫歯の進行から歯が欠けてしまったり、
歯の神経などを抜いてしまって、
折れてしまったもの
・歯並びやかみ合わせの悪さで
歯に負担がかかり欠けてしまったもの
・歯ぎしりにより欠けてしまったもの
治療方法
欠けた大きさなどにもよりますが、
少しだけ欠けてしまった場合は
尖った部分などがないように
歯の形を少し整え、
コンポジットレジンとよばれる
プラスチックの材料で修復します。
また、欠けてしまった部分が大きく、
歯の神経まで到達しているケースだと
痛みを伴うことが多いため、
神経を抜く必要があります。
神経を抜いたあとは、
神経の代わりに薬を詰めて
コンポジットレジンで修復するか、
被せ物をしますが、
欠けた部分がかなり大きく、
歯の根元で折れて引っ張り出せない場合や
縦に歯が折れてしまった場合は
歯を抜かなければなりません。
歯を抜いた後はブリッジや入れ歯、
インプラント治療などを行い修復します。
対処
すぐに歯医医院で受診しましょう。
小さく欠けて痛みが少なくても
鋭利な部分ができてしまい、
口の中を傷つけてしまうことがあります。
歯の状態によっては
その歯を接着することができる場合もあるので
欠けたり折れたりした部分を
歯科医院に持ち込みましょう。
歯が根っこごと抜けてしまった場合も
歯を歯科医院にもって受診してください。
受診までの時間が短く、
歯と骨をつなぐ歯根膜がいきていれば
歯を戻すことができる場合があります。
歯根膜は乾燥に弱く、
約18分乾燥状態になると死んでしまいます。
抜けた歯の保存方法としては、
約24時間歯根膜を生かすことができる
歯の保存液か、
牛乳パックの中にいれて持ち込みましょう。
牛乳は歯の歯根膜を
約6時間生かしておくことのできる、
最適な保存液なんです。
水道水だと歯根膜が生き残るのは
1時間と限定され、2時間経過すると
歯根膜は死んでしまいます。
大事なのは歯にトラブルがあった場合、
すぐに歯科医院で処置してもらうことです。
処置までの時間が短ければ
歯をもとに戻せる確率も高くなるのです。
歯が欠けたり折れてしまう原因の大半が
予想できないアクシデントからきています。
そのアクシデントは
時間や場所を選ばずやってきます。
時間帯や場所が悪く、
歯科医院に行けないからといって、
接着材などを使い自分で対処することだけは
しないようにしましょうね!
欠けた部分が正確に戻らない場合、
咬み合わせの位置がくるって
別の疾患を引き起こすことがよくあります。
歯の欠けや折れもスポーツをする方、
歯ぎしりが強い方は事前にマウスピースという
歯を守る装置もあるので、
そのような装置をつかいながら
予防をしてみるのもいいかもしれません。
急なアクシデントなどで
歯が欠けてしまった時は
まずご連絡下さいね。
詰め物と被せ物
こんにちは。
川崎区小島新田のパール歯科医院です。
本日は詰め物と被せ物について
書かせていただきますね。
虫歯を削り、その削ったところに
詰め物や被せ物をいれている方は
現代において多くいらっしゃるかと思います。
その詰め物や被せ物について
どれだけ認識されていますでしょうか?
詰め物って何?被せ物とは一体何?
そういった疑問についてお答えしていきますね。
詰め物とは軽度の虫歯の治療に使われ、
虫歯になった部分を削り、
削った個所に付けるものです。
それをインレーと呼びます。
被せ物とは虫歯の程度が大きい、
かつ詰め物では補いきれない場合の
治療に使われ、虫歯を削ったあとの
人工の歯として用いられるものです。
それをクラウンと呼びます。
よって虫歯の進行具合や程度により、
詰め物か被せ物のどちらで治療するか
決まってくるのです。
また、上記の詰め物と被せ物には
色々な種類の材質などがあるのをご存知ですか?
Ⅰ保険適用の材質
◆銀合金
(俗に言う銀歯というもので、
金属は金銀パラジウム合金を使用)
インレーやクラウンで使用可
長所
・保険適用で費用が安く、通院数が少ない
短所
・口を開けたときに銀歯がみえてしまう審美的問題
・硬い為噛み合わせの歯を傷つける可能性がある
・長期使用すると錆びて金属イオンが溶け出し、
それが金属アレルギーを引き起こす原因に
なることがある。(銀合金)
◆レジン
(材質は合成樹脂の一種で見た目が白い)
インレーやクラウンで使用可
長所
・保険適用で費用が安い
・見た目が白く少し審美的には良い
短所
・変色や磨り減りやすく、割れやすい
・大きな虫歯には適用できない
◆アマルガム
(水銀20パーセントを含む銀色の詰め物)
20世紀を中心に診療に用いられたが、
昨今、水銀の害が知られ2016年4月より
公的保険治療から外された。
Ⅱ自由診療の材質
◆ゴールド
(俗に言う金歯というもので、
金属は75%~84%の金含有の金合金)
インレーやクラウンで使用可
長所
・天然歯の硬さに近く、噛み合わせの歯を
傷つけることがない
・錆びて金属イオンが溶け出す可能性が低い
短所
・金の高騰により費用がかかる
・セラミックの進歩や審美的な問題もあり、
減少傾向にある。
◆セラミック
(金属を使わない均一のセラミック。
お茶碗の素材)
インレーやクラウンで使用可
長所
・強度に優れ長持ちし、変色しない
・最も天然の歯に近い色調で審美的に優れている
短所
・費用がかかる。
◆ハイブリッドセラミック
(セラミックとプラスチックの混合物)
インレーやクラウンで使用可
長所
・セラミックに比べるとやや安価
・割れにくい
・審美的に悪くない
短所
・セラミックに比べると透明感がなく、
長期的にみるとわずかに変色し磨り減る
◆ジルコニアセラミック
(セラミックのなかで最も硬い。)
クラウンで使用可
長所
・耐熱性、耐久性、耐腐食性が高い
・硬く柔軟性があるので金属を使わずにできる
・体にやさしい
短所
・費用がかかる
このように詰め物や被せ物には
たくさんの種類が存在します。
それぞれ特徴は様々で
自分にはどれが合っているのか?
どれを選べば良いのか?
とわからない方が多いと思います。
そのような時は、
お気軽に歯科医師にご相談ください。
一人ひとりに合った詰め物や被せ物を
ご提案させて頂きます。
入れ歯について
こんにちは。
川崎区小島新田のパール歯科医院です。
お久しぶりの投稿になってしまいました。
今回は入れ歯について書かせていただきます。
入れ歯って何?
まずは入れ歯の歴史から説明しますね。
皆さんは入れ歯がどのくらい前から
使われていたかご存知ですか?
入れ歯は紀元前からさかのぼり、
わが国日本では平安時代のころから
使われていると言われています。
当時の入れ歯は木製でした。
前歯や奥歯が木に彫ってあり、
残りの歯と合うように作られていました。
ちなみにそのころ歯医者さんは
口内医と呼ばれており、
木製の歯を作る人を入れ歯師と呼んでいました。
入れ歯とは歯が根元から
無くなってしまった場合に使うもので、
入れ歯をいれている人が
自ら取り外しを行うことができます。
また、入れ歯は大きく2つにわけられます。
歯が1本も残っていない人が使う
『総入れ歯』
1本以上歯が残っている人が使う
『部分入れ歯』です。
総入れ歯は人工歯と呼ばれる歯の部分と、
歯茎を似せて作る床でできてるものです。
部分入れ歯は人工歯と床があり、
針金や金具で残っている歯に引っ掛けて
安定させるものです。
1本だけ歯を失った人から、
多くの歯を失った人まで
幅広い治療に対応できます。
また、総入れ歯や部分入れ歯には
治療方法や材質、保険適用の有無により
いくつかの種類があります。
プラスチック義歯(保険適用)
長所
1.保険適用がきくので治療費が安い
2.修理しやすい
3.6か月ごとに再製作ができる
短所
1.違和感があり、慣れるまで時間がかかる
2.入れ歯の内側にものが入りやすい
3.発音がしにくい
4.手入れが必要(食後など)
5.材質が弱いので割れやすい
コバルトクロム床義歯(保険外)
長所
1.上の顎が薄い金属でできているため、
口の中が広く感じる
2.熱がアゴに伝わりやすい
3.薄く入れ歯をつくれて強度がある
4.プラスチックの3分の1の薄さなので
違和感がない
短所
1.保険がきかず高価である
2.製作に時間がかかる
チタン床義歯(保険外)
長所
1.軽い(コバルトクロムより軽い)
2.アレルギーが起こらない
(骨に埋め込むインプラントと同じ材質)
3.使用感、装着感がとても良い
4.熱がアゴにつたわりやすい
短所
1.保険がきかず高価
2.製作に時間がかかる
インプラントオーバーデンチャー(保険外)
インプラント(チタン製のボルト)を
約1本~4本アゴに埋め込み、
その埋め込んだインプラントを支えにして
取り外し式の総入れ歯を装置着する方法です。
長所
1.入れ歯の中で1番しっかり噛むことができる
2.アゴの骨に刺激が伝わり、
歯肉やアゴの骨の退縮を抑える
3.使用感が、最も自分の歯に近い
4.バネや複雑な仕掛けがないので
通常の義歯に比べて手入れが簡単
短所
1.外科処置が必要
2.高価である
保険適用の入れ歯は、
ほとんどすべての方が受けられる治療ですが、
従来の入れ歯はすべての方が
満足できる治療とは限りません。
それにより材質や治療方法を変え、
入れ歯のデメリットを
メリットにかえることはできますが、
歯を失ってから治療を考えるのではなく、
歯を失わないよう、予防を心がけることが
大事だと思います。
歯を大事にして、
いつまでも健康で素敵な笑顔が絶えない
人生を送ってみてはいかがでしょうか?
入れ歯に関して、
不明な点や疑問点がありましたら、
いつでもお気軽にご相談くださいね。
お問合せ・ご予約はこちら
ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話いただき初診のご予約をいただくか、 下記の「無料相談メールフォーム」に相談内容をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。 電話やメールではお答えするのが難しい場合には、初診のご予約をお願いする場合があります。 また、初診はすべて保険内での診察となります。
メールフォームでのご相談
ご予約前のご質問や疑問に
メールでお応えします
※電話での無料お悩み相談は承っておりません。
診療中にお受けしてしまうと、他の患者様にご迷惑をお掛けしてしまいますので、ご理解の程お願い申し上げます。